「もっと勉強しなさい」「いい大学に行けば、将来困らないから」——かつて私たちが親から言われてきた言葉です。
学歴が人生を左右すると信じ、競争の中で育ってきた私たちは、いつの間にか「良い成績=幸せ」という価値観を刷り込まれていました。
けれど、いざ自分が親になり、子供の進路や学力について悩む日々の中で、ふと立ち止まる瞬間があります。「あの価値観は、本当に正しかったのか?」「自分は今、幸せか?」と。
私はシングルファーザーとして、大学生の長男と高校生の長女を育てています。
成績のことで悩んだ日々もありました。しかし今は、彼らの成績よりも「どんな人生を選ぶのか」「どう生きていくのか」を大切に見守っています。
この記事では、学歴社会に生きてきた世代の親が、なぜ「子供の成績を気にしない」という選択に至ったのか。
その背景にある価値観の変化や葛藤、そして見えてきた希望について、私自身の経験を交えて綴っていきます。

👉他にも、生活・暮らし・経済に関する記事がありますので、ぜひご覧ください。
>>>ジャングル東京で遊ぶには?料金やコース別のシミュレーションをしてみた
第1章:学歴神話に育てられた私たちの世代
私たちが育った時代には、「いい大学に行けば、人生は安泰」という考えが当たり前のように存在していました。
両親や先生たちは、偏差値という数字を人生の成功の指標のように扱い、それが自分の価値を決めるものだと信じ込ませてきました。
塾に通うのが当たり前で、模試の順位や合格実績が、家庭の会話の中心になることも珍しくありませんでした。
実際、私は必死で勉強し、それなりの大学に進学しました。
親の期待に応えることが「正しい人生」だと思っていました。模範的な道を歩くことが、将来の安定や幸福につながると信じて疑わなかったのです。
しかし、社会に出て感じたのは、学歴だけでは得られない「生きる力」の重要性でした。
仕事や人間関係、人生の選択には、学力ではなく、柔軟さや自分で考える力が求められたのです。
与えられた課題に答える力ではなく、課題そのものを見つけ出し、周囲と協力しながら乗り越えていく力。それこそが、本当に求められる能力であることを痛感しました。
この違和感は、私が親になったとき、改めて強くなっていきました。
自分が正しいと信じてきた価値観を、我が子にそのまま当てはめてよいのか。そんな疑問が、次第に私の中に芽生えていったのです。
第2章:親になって見えてきた「幸せ」とは何か
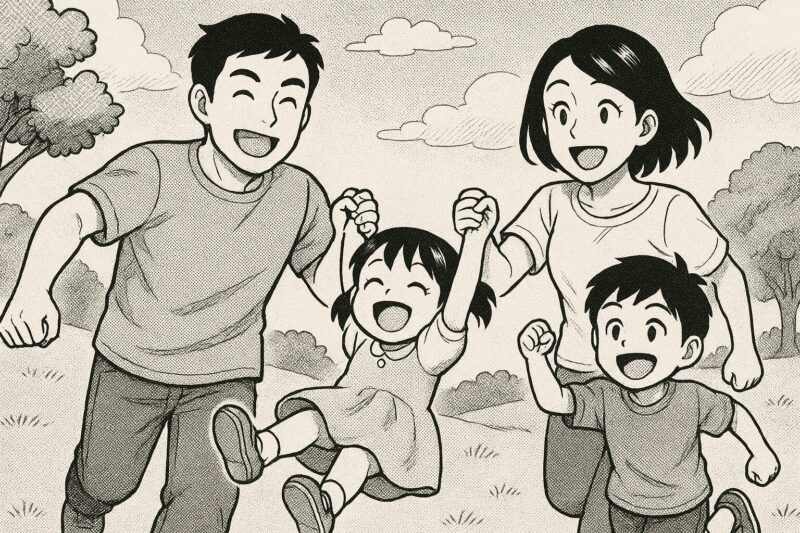
子供が成長していく中で、成績の良し悪しに一喜一憂する日々が続きました。
テストの点数、通知表の評価、周囲の子供との比較……。
自分でも驚くほど、数字に振り回されていたことに気づきました。
点数が良ければ安心し、悪ければ不安に駆られる。
その繰り返しの中で、私は無意識のうちに、成績を「子供の価値」と混同していたのかもしれません。
けれど、ある時ふと、「自分が求めているのは、子供の“幸せ”なのか、それとも“安心”なのか」と考えるようになりました。
親としての安心を得たいがために、成績という“見える成果”に頼っていたのかもしれません。
実際には、子供の未来を真剣に思っていたのではなく、自分自身の不安を紛らわせたかっただけではないか。
そう思い至ったとき、胸が締めつけられるような気持ちになりました。
子供が笑っている日々、自分の好きなことに没頭している姿を見て、「これが本当の幸せではないか」と思えるようになりました。
成績では測れない個性や情熱に目を向けたとき、初めて私は「この子はこの子のままでいい」と心から思えるようになったのです。
そこから、親としての私自身のあり方も少しずつ変わっていきました。
第3章:成績よりも「選択する力」を育てる
私が今、最も大切にしているのは、子供が「自分で選ぶ力」を持つことです。
大学に行くか行かないかも、自分で決める。どんな職業を目指すかも、自分で考える。
その意思決定の中には、迷いや葛藤、周囲からのプレッシャーも当然あるでしょう。
しかし、それらすべてが、子供にとってかけがえのない成長の糧になると信じています。
もちろん、選択には責任が伴いますし、失敗することもあるでしょう。
選んだ道が思い通りに進まず、後悔や挫折を味わうこともあるかもしれません。
それでも、それも含めて「自分の人生」なのだと思います。
誰かのせいにできないからこそ、自分で責任を持ち、乗り越えたときに得られる達成感や自信は、何ものにも代えがたい価値があります。
親が与えたレールの上をただ歩くだけではなく、自分の足で道を探し、時に迷いながらも前に進んでいく。
その過程こそが、何よりも価値ある経験になるのです。
そして、そうした経験を通して、自分の価値観や生き方を見つけ出していくことこそが、教育の本質なのではないかと思います。
第4章:成績を気にしないことへの不安と向き合う
「本当にこのままで大丈夫だろうか?」という不安は、今でも心のどこかにあります。
周囲の親たちが塾や進学の話をしている中で、取り残されているような感覚になることもあります。
SNSやママ友との会話でも、進学先や模試の結果が話題になるたびに、私の中に湧き上がる不安は小さくありませんでした。
それでも、私は「信じる」ことを選びました。子供の力、成長の過程、そして、自分の選択を。
信じることは簡単なようでいて、実はとても難しいことです。
子供を信じるには、自分自身をも信じる必要がありました。
自分の価値観、そして子供に対する見方や接し方に、自信を持てるようになるまでには時間がかかりました。
不安はゼロにはなりませんが、それでも「親が安心するための教育」ではなく、「子供が幸せに生きるための教育」を目指したいと思っています。
幸せとは何か、それは点数や偏差値ではなく、子供が自分らしく、納得しながら人生を歩んでいけること。
私はその土台を育てるために、今できることを、焦らず誠実に積み重ねていきたいと思っています。
第5章:自分らしく育った子供が教えてくれたこと
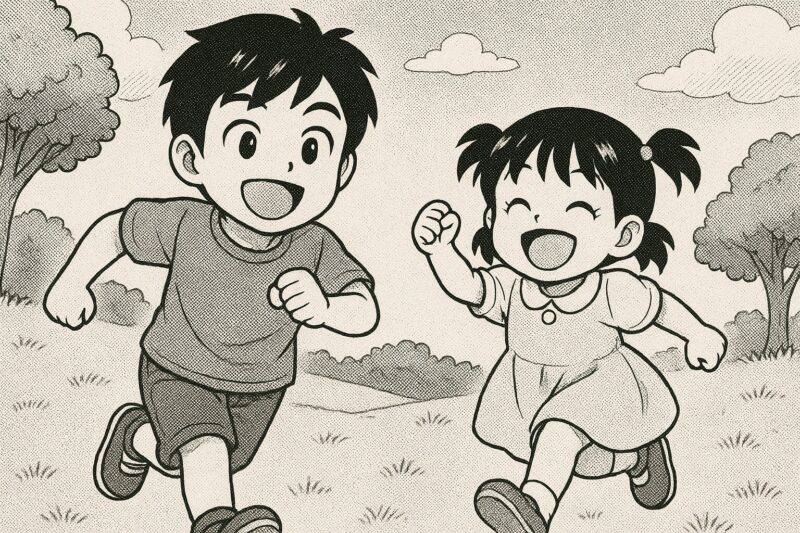
大学に進学した長男は、自分の好きな分野に夢中になり、毎日が充実している様子です。
専門書を手に取ったり、授業以外でも自主的に学んだりと、自分の興味を深めながら日々を過ごしています。
時には課題に悩みながらも、そのプロセスさえ楽しんでいる姿を見ると、私自身も元気をもらうことがあります。
高校生の長女も、自分なりに未来を模索しながら、自由に成長しています。
彼女は最近、アートに関心を持ち始め、学校外のワークショップに参加するようになりました。
その中で、自分の表現したいことや、興味の方向性を見つけつつあるようです。
勉強だけにとらわれず、多様な体験を通じて、視野を広げている姿に頼もしさを感じます。
彼らの姿を見て、「信じてよかった」と心から思えます。成績や偏差値に縛られず、自分のやりたいことを追いかける姿には、私自身も学ばされることが多いです。
子供たちのひたむきな姿勢は、日々の小さな選択の中に確かな成長があることを教えてくれます。
親ができることは、完璧な道を示すことではなく、子供が選んだ道を肯定し、支えることなのだと気づかされました。
例え遠回りに見えても、自分で決めた道なら、きっとその先には自分だけの答えがある。
その確信が、私の不安を少しずつ和らげてくれています。
まとめ:成績よりも、人生をどう生きるか
「子供の成績を気にしない」という選択は、簡単なことではありません。
不安もありますし、周囲とのギャップに戸惑うこともあります。
特に周囲の親たちが進学塾や成績アップの話題で盛り上がっている時、自分の選択が間違っているのではないかと揺らぐ瞬間もあります。
それでも、私は「子供の人生は子供のものだ」という信念を大切にしたいと思っています。
親が押しつけた価値観ではなく、自分自身で選び取った人生を生きてこそ、本当の意味での幸せがあるのではないでしょうか。
子供が自分の道を歩く姿を見るたびに、安心と誇りのような感情が湧いてきます。
成績よりも、自分らしく生きる力を。学歴よりも、人生を選びとる勇気を。これは、決して抽象的な理想論ではなく、日々の選択の中で確かに育まれていくものだと感じています。
時にはつまずくこともあるでしょう。ですが、その経験こそが人を強くし、豊かにしてくれるのです。
親として、これからも子供たちを信じて、見守っていこうと思います。
目の前の結果だけでなく、長い人生の中で彼らがどう成長し、どんな喜びを見つけていくのかを見届けること。
それが、親としての本当の幸せなのだと、私は思います。
👉他にも、生活・暮らし・経済に関する記事がありますので、ぜひご覧ください。
>>>ジャングル東京で遊ぶには?料金やコース別のシミュレーションをしてみた
最後まで読んで頂き、有難うございました。


コメント